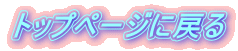*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『図解近畿の城郭Ⅳ』の図を参考にした。若江城の場所
若江城は若江町の住宅街の中にある。
周囲は都市化が進んでおり、遺構は壊滅状態である。
かつての城内に若江鏡神社が祀られており、その前に城址碑が建てられているのが、唯一城址を示しているものである。
上記の書には発掘で検出された堀から想定した復元図が掲載されており、それに基づいて鳥瞰図を作成してみると、右の図のようになる。
中心となっている1は150m四方ほどの規模があり、中世城館の主郭としてはけっこう広い。
内部からは石垣・礎石建物などが検出されている。
その周囲に堀に囲まれた複数の郭があったと想像されるのであるが、検出された堀が部分的なものばかりで、全体構造を復元することは困難な状態である。
それでも、かなり規模の大きな城だったのではないかという気がする。
若江城がいつ築かれたのかは不明である。
史料に最初に現れてくるのは、寛正元年(1460)9月に京都を追われた畠山義就が、若江城に入城したという記事である(『長禄記』)。
ここには「四方は皆深田にて、口二つにして所々を堀切て掻楯、木戸、逆茂木思の儘に拵へて」と、城の様子を示す具体的な記述があり、興味が惹かれる。
文明9年(1477)、応仁・文明の乱が終結すると、畠山義就は京都の陣を引き払い、河内へ下向する。その際に若江城を攻略しようとした。
当時若江城は、畠山政長方の遊佐長直が守っていた。
政長は騎兵3500、歩兵200余という大軍で若江城を攻撃、10月10日には落城した。遊佐長直は天王寺から船で脱出した。
永禄年間になると若江城は三好方の城となっていた。
永禄13年には三好義継が若江城主となっており、松永久秀は若江に礼に赴いている(『二条宴乗記』)。
天正元年(1573)7月、槙島城で反旗を翻した足利義昭は、結局は敗れ信長に投降することとなった。
槙島城を追われた義昭は若江城の三好義継に迎えられた。
同年11月、信長は佐久間信盛に若江城を攻めさせた。三好義継の家臣で若江三人衆と呼ばれた池田教正・野間長前・多羅尾綱知は、織田方に寝返って佐久間勢を城内に導き入れた。
これによって若江城は落城し、義継は自害した。
『信長公記』には「天主の下まで攻め込み候のところ、叶ひがたくおぼしめし」とあり、若江城に天守があったことが知られるが、『信長公記』は、これ以外にも中世城郭で「天主」という語句を多用しており、『信長公記』における天主とは、主に主要な建造物といった意味で使われているのではないかと思われる。
その後の若江城は若江三人衆に預けられ、信長の石山本願寺攻撃の際の拠点となった。