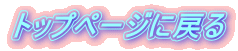鹿児島県いちき串木野市
*参考資料 『日本城郭大系』 『鹿児島県の中世城館跡』
*参考サイト 城郭放浪記
串木野城・串木野麓(いちき串木野市麓)
 *鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
串木野城の場所。 串木野麓駐車場。
串木野城は南九州自動車道串木野ICの西方300mほどのところにある。
城址の南側の県道を走っていると「串木野麓駐車場→」と書かれた案内が建てられているのが分かる。これにしたがって、北側に進んで行くと、串木野麓の下の部分に出る。駐車場が用意されているので、車はそこに停めて歩いて回るとよいだろう。
駐車場の北側の長谷川純孝生誕の地とある部分も串木野麓の一部だったのではないかと思われる。
そこから北側に進んで行くと高い石垣が正面に見えてきており、そこに地頭仮屋跡の案内板が立てられている。この背後の石垣の上が串木野麓の中心部だったと思われる。内部は住宅街となっている。
この石垣に沿って北上していくと、串木野城の案内板が出ており、そこが城内への入口となっている。
進んで行くと登城道は2郭と3郭との間に通じている。そこから2郭と3郭とに上がって行く道がそれぞれ付けられている。
3郭の入口には方形の窪んだ地形がみられる。小規模ながらこれは枡形虎口だったようで、同様の構造物は1郭や、3の北の郭などにも見られる。
2郭と3郭との間の堀底道をさらに進んで行ったところが1郭で、1郭城塁が正面に高くそびえて見えている。遊歩道が整備されているのはここまでで、1郭の堀は倒竹だらけになってしまっている。
城塁も急峻で正面から登って行くのは無理である。1郭に上がるには側面部に回り込んで、何とかよじ登れそうな場所を探すしかない。
先の登城道を戻り、3郭と東側の細長い郭との間の通路を抜けて行くと、3の北側の郭との間の堀の所に出る。
この郭のさらに先端部から北西に細長く延びた郭群が存在していたようだが、この部分は現在は削られ住宅地と化している。
城の東側の道路を挟んだ東側には南方神社のある高台がある。これも串木野城の郭の1つであり、背後には土塁が残されている。
間の道路を少し進んだところには日高どんと呼ばれる箇所がある。日高氏の屋敷が営まれていた所であったろう。現在は日高美容室となっている。
このように〇〇どんといった屋敷名は他にも残されている。
中でもセカイ飯田どんとモタイ屋敷のところにはかつては堀や土塁が残されていたようであるが、現在ではこの部分の遺構も消滅してしまっている。
このように串木野城は南九州地区によく見られる群郭式の城郭の1つであった。
串木野麓跡は、現在の串木野城が築かれる以前には串木野氏の居館があった場所ではないかと想定されている。
なお、串木野麓の石垣は明治30年に築かれたものだとのことで、これは遺構ではない。
 |
 |
| 神社との間の堀跡。 |
4郭の南方神社。 |
 |
 |
| 土塁。 |
案内板と主要部への入口。 |
 |
 |
| 堀。 |
堀。 |
 |
 |
| 堀。 |
2郭。 |
 |
 |
| 土塁。 |
3郭。 |
 |
 |
| 枡形虎口。 |
3郭。 |
 |
 |
| 石積み。 |
3郭の北側の郭。 |
 |
 |
| 1郭堀。 |
堀。 |
 |
 |
| 堀。 |
1郭。 |
 |
 |
| 堀。 |
堀。 |
串木野城は、鎌倉時代に串木野三郎忠道によって築かれたのに始まる。 以後は串木野氏の居城となるが、当時の串木野城は居館程度のものだったと思われる。
南北朝時代の康永元年・興国3年(1342)、島津貞久は市来鶴丸城主の時家を降伏させ、その勢いで串木野城にも攻め寄せた。
この戦いで串木野忠秋は城を明け渡して知覧へ逃れた。
串木野城は島津氏の所領となり、文明年間(1469〜87)には島津家臣の川上忠塞が城主となった。
以後、川上栄久、忠克と続く。
天文8年(1539)、川上忠克は島津忠良と対立した島津実久に加担したため、忠良に攻められ降伏した。忠克は甑島に配流となってしまう。
川上氏の後は、山田有徳、有信が串木野地頭を務めた。
元亀元年(1570)、島津貴久の4男家久が隈之城地頭となると串木野の地頭も兼ねることとなった。
天正7年(1579)、家久は日向国佐土原へ転封となり、その後は仁礼隼人が串木野地頭となった。 |
 |
 |
| 串木野麓の石垣。明治30年に築かれたものだという。 |
案内板。 |
 |
 |
| 長谷川純孝生誕の地。 |
内部。 |
 |
|
| 城への案内。 |
|
|
鍋ヶ城(いちき串木野市大里)
 *鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
鍋ヶ城の場所。
鍋ヶ城は大里川の北側にある比高20mほどの独立台地に築かれている。台地内部は一面の畑となっており、車で上がって行くことも可能である。
この台地上が城址ということであるが、台地上は長軸250mほどもありだだっ広い。全面的に耕作地となっているためか堀などの遺構を見ることもできない。
これで単郭だとしたらあまりにも広大になりすぎるので、本来は内部はいくつかに区画されていたのではないかと想像する。
中央を通っている道路の北側がやや高くなっているので、この部分がかつての区画の名残なのかもしれない。
広大な畑の真ん中に惟宗広言の墓が残されていた。これが唯一城に関する遺物ということになろうか。
側面部には民家が建てられている平場などもあるが、城の遺構の一部なのかどうかは不明である。
鍋ヶ城は、平安時代初期の宝亀年中に大蔵政房が薩摩に下向して市来院郡司となって居住したのに始まるという。
市来家房は外孫の惟宗政家に郡司職を譲ってから、惟宗姓を名乗るようになった。以後は惟宗氏の居城となる。
惟宗氏は後に、市来鶴丸城に移転し、以後は廃城となったと考えられる。
 |
 |
| 東方から。 |
城内。 |
 |
 |
| 惟宗広言の墓。 |
山麓の切通し。 |
|
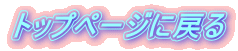
 *鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
























 *鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。
*鳥瞰図の作成に際しては『鹿児島県の中世城館跡』の図を参考にした。